1. 概念から「具体」へ:二冊の図鑑が示す解像度
前回は、備瀬崎の海が持つ「静と動」の対比、そして「おさかな図鑑」を通じた多角戦略について語りました。そして今、私の手元には、その戦略を具現化する二冊の「沖縄の知恵」があります。
- 沖縄タイムズ社の『沖縄さかな図鑑』:体系的で広範な「水産資源」としての沖縄の海。
- 沖縄マリン出版の『沖縄魚図鑑』:ダイビングやシュノーケリングで楽しむ「海中の楽園」としての沖縄の海。
この二冊は、単なる情報の羅列ではありません。前者は「移住後の生活を支える確固たる基盤(情報と計画)」を、後者は「日々の暮らしを彩る豊かな感性(人と思索)」を教えてくれます。まさに、私の「第二章」を支える「知恵の二刀流」戦略そのものです。
2. 「情報(柱IV)」の深化:知識の統合と新たな発見
『沖縄さかな図鑑』の734種という網羅性と、漁業・資源管理に関する解説は、備瀬崎BASEプロジェクトの「情報(柱IV)」に、これまで欠けていた「体系的な裏付け」をもたらします。
一方で、『沖縄魚図鑑』が持つ沖縄での呼び名や料理・食べ方の情報は、地域住民との交流を深めるための「対話のきっかけ」となるでしょう。地元の言葉で魚を語り、その食べ方を共有する。これこそが、「人(柱I)」のコミュニティ戦略を円滑に進めるための重要な布石です。
この二冊の知識を私の「おさかな図鑑」に統合することで、以下のような新たな視点が生まれます。
- リスクと豊かさの同時理解: オルダルマオコゼの危険性と共に、地域における魚の「水産資源としての価値」を深く理解する。
- 「幻のターゲット」の再定義: 絶版図鑑にしかない、特定の場所でのみ見られる「幻の魚」の情報から、新たな「発見」の目標を設定する。
3. 「心の羅針盤」としての図鑑:戦略と感性の融合
この二冊の図鑑は、私にとって単なるデータ集ではありません。それは、来年7月の家族旅行、そしてその先の移住に向けた、私の「心の羅針盤」です。
私がビジネスで培った「冷徹な分析力」と、備瀬崎で育みたい「豊かな感性」。この二つを融合させることこそが、「時間の質」を追求する「第二章」の真髄です。
米国出張中も、この二冊の図鑑がもたらす「沖縄の知恵」を胸に、仕事の合間に未来の計画を練り続けます。異国の地で、異なる文化に触れることで、沖縄の魅力、そして「BISEZAKI BASE プロジェクト」の意義が、より一層鮮明になることでしょう。
次回は、米国出張での新たな発見や、現地での思考の進捗についてお話しできればと思います。
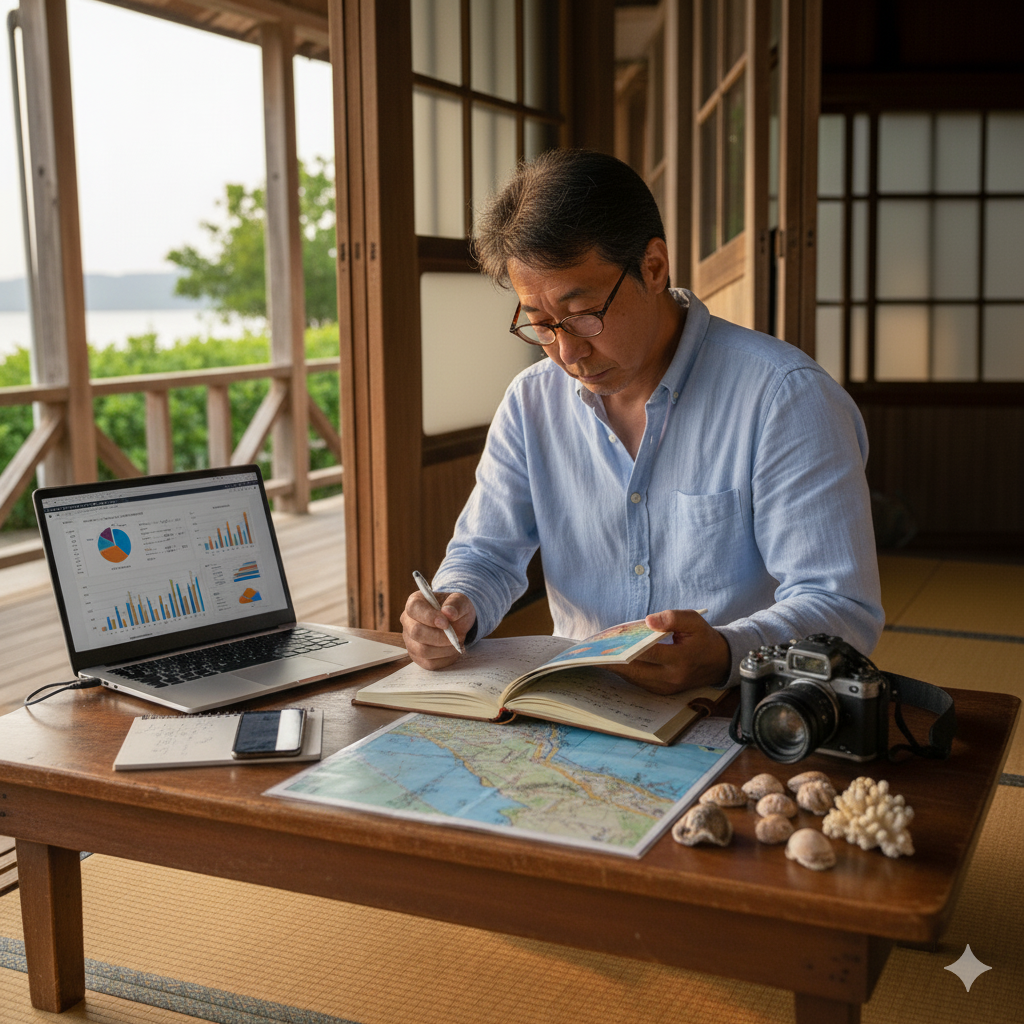


コメント